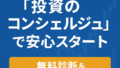投稿日:2025年8月1日
はじめに
ビットコインなどの暗号資産が話題になって久しいですが、「なぜ高値がついているのか」「価値の裏付けはどこにあるのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、暗号資産の「価値」の正体について、法定通貨との比較や具体例を交えながらわかりやすく解説します。
暗号資産の「価格」と「価値」は別物?
まず押さえておきたいのは、暗号資産の「価格」と「価値」は同じではないということです。
ビットコインの価格は、これまでに何度も乱高下を繰り返してきましたが、それでも価値が支持されている背景には明確な理由があります。
最大のポイントは「多くの人が保有し、支持している」こと。日本国内だけでも口座数は1,200万を超え、世界では6.5億口座と推定されています。
これは単なる投機対象ではなく、人々がビットコインを「資産」として認識している証拠です。
物理的裏付けのない「デジタル資産」に価値がある理由
ビットコインの実体は、あくまでデジタルデータです。有体物ではないため、日本の民法上は所有権の対象にはなりません。
にもかかわらず、1BTC=1,200万円前後で取引されているのは、「将来もっと高く買ってくれる人がいる」と多くの人が信じているからです。
この構造は、実は法定通貨と非常によく似ています。
日本円も、現在は金などの資産と交換されるわけではなく、紙幣1枚の原価は20円未満。それでも私たちは「1万円札に1万円の価値がある」と信じ、日常的に使っています。
法定通貨と暗号資産の共通点は「信用」
ここで重要になるのが、「信用」の存在です。
法定通貨は国家の権限(徴税権や中央銀行の存在)によって価値を維持しています。
一方、ビットコインは国家ではなく、グローバルなユーザーの「市場による信用」に支えられています。
信用が崩れれば価値も崩壊する
たとえば、ハイパーインフレが起きて「明日は1万円で買えた物が2万円になる」と多くの人が思うようになれば、1万円札の価値は暴落します。
同じように、ビットコインも「もう誰も買わない」と思われれば価値はゼロになるでしょう。
つまり、どちらも「みんなが価値があると信じているからこそ価値がある」のです。
ビットコインの発行上限と信用の関係
ビットコインが他の暗号資産と異なる最大の特徴は、「発行上限」が明確に定められていることです。
その上限は2,100万BTC。2140年頃までにすべてのビットコインが発行され、新規発行は終了します。
この上限により、供給過多になることがなく、インフレを抑制できるという期待感がビットコインの信用を高めています。
現時点で、すでに約1,980万枚が発行済みであり、流通量も一定しています。
米国政府の動きが象徴する「ビットコインの別格扱い」

2025年3月、アメリカのトランプ大統領は暗号資産の国家備蓄に関する大統領令に署名。
このなかで、ビットコインは「Reserve(準備資産)」として明確に区別されました。
実際に、米政府がこれまでに没収した約20万枚のビットコインは売却されず、保有が継続されており、将来的には追加購入の可能性も示唆されています。
一方、イーサリアムやその他の暗号資産は「Stockpile(備蓄)」扱いとなり、必要に応じて売却される可能性があるという違いが明確にされています。
今後は「ビットコイン=金融資産」「他の通貨=Web3トークン」に?
このような政府レベルでの動きからも、ビットコインは金のような「価値の保存手段」としての地位を確立しつつあります。
一方、イーサリアムなどはWeb3の中で使われる「ユーティリティトークン」としての色合いが強まっていくでしょう。
筆者による視点とアドバイス
なぜ「信用」が価値になるのか?
本記事で取り上げられていたように、ビットコインの価値は「信用」によって成り立っています。
では、なぜ人はそのような「信用できる仕組み」を信頼するのでしょうか。
それは、従来の金融システムに対する不安や、将来に備えた分散的な資産形成への関心が年々高まっているからです。
実際、2020年代以降は中央集権的な金融機関や政府の動きに対して批判的な目が向けられ、代替手段としての「非中央集権型の通貨」が注目されてきました。
ビットコインはその象徴とも言える存在であり、プログラムにより供給量が固定されている点などが、多くの人にとって「信頼できる」と感じられる要因となっています。
資産形成としてのビットコイン、どう向き合えばいい?
では私たちは、このような暗号資産とどう向き合えばいいのでしょうか?
ここで大切なのは、「短期的な価格の上下に振り回されないこと」です。
ビットコインはボラティリティ(価格変動)が大きい資産です。
長期視点での資産の一部として考えるのが現実的でしょう。
たとえば、以下のような姿勢が現実的です。
- 生活資金や生活防衛資金とは分けて、投資余力の範囲内で少額から始めてみる
- 価格に一喜一憂せず、月1回など定期的に積み立てる(ドルコスト平均法)
- 暗号資産は資産全体の10〜20%程度にとどめ、株式や現金、投資信託などとバランスを取る
また、ビットコインとその他の暗号資産(アルトコイン)ではリスクや用途が異なる点も意識しておきたいところです。
前者は「デジタルゴールド」に近く、後者はWeb3やNFTなどの「ユースケース」に紐づくことが多いです。
どちらにせよ、よく仕組みを理解したうえで、自分に合った資産形成手段を模索していくことが大切です。
参考文献
- ZUU online:暗号資産の「価値」はどこから来るのか?
- 小田玄紀 著『デジタル資産とWeb3』(アスコム)